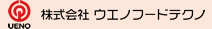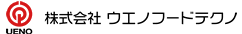皆様から頂戴するご質問にカテゴリ別にお答えしています。(カテゴリを選択してください)
食品添加物の安全性について
- Q1.
- 食品添加物をどのくらい摂ると、身体のどこを害するのですか?
- A.
- まず、どのようなものでも摂りすぎると健康に悪影響があります。砂糖を摂り過ぎれば糖尿病のおそれがありますし、食塩だと高血圧などのおそれがあります。ヒトに健康影響があるかどうかは、量によって決まります。
食品添加物は、一生毎日摂り続けても安全と考えられる量(一日摂取許容量:ADI)が求められています。そして、その量を大きく下回る量しかヒトに摂取されないように、必要に応じて使用できる食品や量が決められています。実際にヒトが摂取している食品添加物の量も調べられており、健康に影響するような量が摂取されていないことが確認されています。
したがって、身体を害するような量の食品添加物を摂ることは実質的には考えられません。安心してバランスの良い食生活を楽しんでいただければと思います。
<参考リンク>
●05 食品添加物の安全性 > #1 安全性はどのように評価・管理されているか
- Q2.
- どの食品添加物は避けた方が良くて、どの食品添加物であれば問題ないのですか?
- A.
- 食品添加物は、ヒトの健康に悪影響のない量しか使わずに、食品中で有用な働きをするもののみが使用を許されています。また必要に応じて、使うことのできる食品の範囲や使うことのできる量が決められています。したがって、避けた方が良い食品添加物というものを心配される必要はありません。
- Q3.
- 食品添加物は体内に蓄積して、何年も経ってから健康に悪影響を及ぼすのではないでしょうか?
- A.
- 食品添加物が体内に蓄積して健康に悪影響を及ぼしたという例はこれまで報告されていません。新たに食品添加物として許可されるためには、ヒトでの代謝を推定する試験など種々の動物実験から、ヒトが一生食べ続けても健康に悪影響はないと評価されることが必要です。
例えば、代表的な保存料であるしらこたん白は、小腸でアミノ酸(私たちの身体の構成成分です)にまで分解・吸収されると考えられています。したがって、体内に蓄積されることはありません。
- Q4.
- ヒトの身体に化学物質は摂取しない方が良いのではないですか?
- A.
- まず、食品は化学物質の集合体であるということをご理解ください。普段耳にするたん白質とか脂質とかいう言葉も、ある種類の化学物質の総称です。また、普段耳にしないような化学物質も食品には多種類含まれています。食品は多様な化学物質を含んでおり、それらのうち健康影響が評価されているものはほんの一部です。
一方で、食品添加物は健康への影響が評価された上で許可されています。適切に使用する限り、健康に悪影響を与えることはありません。
<参考リンク>
●どうして合成の食品添加物を使うのですか。天然の物で代用できないのですか。
- Q5.
- 現在使用が許可されている食品添加物の中で、わずかでも毒性があるものはどれですか。
- A.
- わずかでもリスクのあるものということでは、ほとんどの食品があてはまります。例えば、ニンジンやレタスにはカフェ酸、パイナップルにはアクリル酸エチルが含まれており、どちらも発がん性がある可能性があるとされています。
しかし、ニンジン等を食べてがんになるわけではありません。これらの化学物質の「量」が少ないからです。食品のリスクを考える時にはどのくらいの「量」で健康影響が出るのか、実際にどのくらいの「量」を食べるのかを考えることが大切です。
食品添加物はどのくらいの「量」なら健康に悪影響を与えることなく使用できるかが調べられ、管理されています。適切に使用する限り、健康に悪影響が出るような量を摂取することはありません。
- Q6.
- 食品添加物は世代を超えた影響はないのですか?
- A.
- 繁殖試験といって、実験動物に二世代にわたって食品添加物を与え、交尾率、妊娠率、出産率、離乳時の生存率を評価する試験が行われています。また、妊娠中に食品添加物を摂取した際の胎児の発生、発育に対する影響、奇形の発生を評価する催奇形性試験もあります。これらの試験により、食品添加物摂取が世代を超えた影響を及ぼさないか調べられています。また、食品添加物の多くは天然の食品にも含まれている物質ですので、心配は少ないと考えられます。
<参考>
●「食品添加物を正しく理解する本」小見邦雄、山田隆、西島基弘共著、工業調査会(2002)
- Q7.
- 子供達に食べさせても何の影響も無いのでしょうか。
- A.
- 年齢や個人差も考慮して一日摂取許容量(ADI)は設定されています。小児における食品添加物摂取量の調査結果においても、問題ない量であることが報告されています。
<参考リンク>
●「ADI(一日摂取許容量)」とは何ですか?
●05 食品添加物の安全性 > #2 実際に食品添加物を摂取している量
- Q8.
- 食品添加物には発がん性があるのではないですか?
- A.
- 食品添加物では、動物実験により発がん性の有無が調べられています。その結果、食品安全委員会で審査され、安全である評価の得られたものだけが厚生労働省の薬事・食品衛生審議会でさらに審議され、食品添加物として使用が許可されます。
いわゆる天然添加物(現在は既存添加物に分類)の中には、十分な安全性評価が済んでいないものもあり、現在評価が進められています。これまでに251品目(H27.6月現在)が安全であると評価されましたが、発がん性が疑われたアカネ色素という天然色素については速やかに使用禁止とされました。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #1 食品添加物とは > 食品衛生法による分類
- Q9.
- アレルギーとの関係が気になります。
- A.
- 実は、食品添加物の多くは天然の食品にも含まれている成分であり、食品添加物も食品と同様にアレルギーの原因になる可能性はあります。ただし、食品添加物が許可される際にはアレルギーの原因になるかどうかが調べられますので、食品よりもむしろアレルギーの原因となる可能性は低いといえます。
アレルギーは通常分子量の大きいたん白質で起こります。合成由来の保存料にはそのような大きな分子量のものはありません。天然由来ではたん白質系のものもあり、例えばしらこたん白抽出物が挙げられます。ニシン由来のものとサケ由来のものがありますが、サケはアレルギー表示が推奨されていますので、サケ由来のしらこたん白抽出物を使用した場合は「保存料(しらこたん白抽出物:サケ由来)」等のように表示されます。
- Q10.
- 複数の食品添加物を同時に摂ると、複合汚染の心配はありませんか?
- A.
- 食品添加物は、ヒトの健康に悪影響のない量しか摂取されないように使用基準が定められています。理論的には、影響のないものを何種類摂取してもヒトの身体にはやはり影響がないと考えられています。
また、「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」(食品安全委員会、平成18年)では、個々の食品添加物として評価されている影響を超えた、複合的な影響が出ている事例は見出されないと報告されています。
- Q11.
- どうして合成の食品添加物を使うのですか。天然の物で代用できないのですか。
- A.
- まず、天然・合成といった由来に関わらず、同じ物質は同じものです。安全性についても、もちろん差はありません。実際に天然由来と合成由来とで同じような食品添加物が許可されている事例もあります。安息香酸は合成由来の保存料ですが、天然由来のエゴノキ抽出物の主成分も安息香酸です。
※エゴノキ抽出物は、流通実態がないとして2011年に消除され、現在では使うことができません。
一般的に、合成品は均一な品質を維持しやすいですが、天然由来だと産地の違いや気候の変動によって成分が異なってくる可能性があります。また、必ずしも原料由来の不純物を除去しきれない場合もあります。したがって、天然品だから安全ということはなく、合成品と同様に(あるいはそれ以上に)品質や使用量に注意する必要があります。
- Q12.
- 過去に食品添加物による事故はありますか?
- A.
- 1955年のヒ素ミルク事件が挙げられます。この事件では、近畿、中国地方を中心に赤ちゃん用の粉ミルクを飲んでいた子供に、発熱、下痢、発疹、皮膚に色素が沈着して黒ずむなどの症状がでました。患者数1万名以上、死者130名に達した痛ましい事件です。
当時は食品添加物の成分規格等がまだ整備されておらず、許容量以上のヒ素が含まれていたリン酸塩が食品に使用されたことがこの事件の原因でした。その後、食品添加物の成分規格、試験方法等を記載した「食品添加物公定書」が刊行され、それ以降は同様の事件の報告はありません。
- Q13.
- 食品添加物を摂り過ぎて病気になった例はありませんか?
- A.
- 適切な量を用いる限り、食品添加物がヒトの健康に悪影響を及ぼすおそれはきわめて小さいといえます。しかし、過去に食品添加物を使いすぎたことによる事故が発生しています。
1960年代にズルチンという甘味料の大量使用による事故が起こりました。ズルチンは砂糖の200倍以上の甘味があるので、通常は大量に加える必要はありません。砂糖や片栗粉との誤用が事故の原因だったと言われています。その後ズルチンは食品添加物から削除されています。
1980年代にはニコチン酸で事件が起こっています。ニコチン酸は栄養強化目的で使われるビタミンの一種ですが、肉の色を新鮮な時と同じように保つ効果も持っているため、挽肉等に大量に使用されたそうです。現在では、ニコチン酸は食肉および鮮魚介類(鯨肉を含む)に使用してはならないとされています。
<参考資料>
●「食品添加物を正しく理解する本」小見邦雄、山田隆、西島基弘共著、工業調査会(2002)
- Q14.
- 細菌を殺すような保存料は、人間にも影響があるのではないでしょうか?
- A.
- ヒトの健康に影響のない量で、食品中の細菌等の増殖を抑制することのできるもののみが、保存料として使用を許可されています。
また、保存料は細菌を殺すのではなく増殖を抑制するものですし、大腸到達時の濃度はきわめて低いので、保存料がヒトの体内の有用菌を殺すといったことはありません。
- Q15.
- pH調整剤を摂取すると体内のpHが変わってしまいませんか?
- A.
- 食品添加物として摂取するpH調整剤で体内pHが変わることはありません。
- このページのトップへ
食品添加物の有用性について
- Q16.
- 保存料は食品の保存の他にどのような有用性がありますか?
- A.
- 保存料が添加された加工食品は、遠くでつくられたものであっても手軽に買えるという便利な食生活に役立っています。またこの加工食品の普及のおかげで家庭での調理の時間が減り、その分の時間を個人的な仕事や趣味にあてる時代になってきています。このようなライフスタイルの多様化にも保存料がその一助を担っています。
<参考リンク>
●02 食べ物の腐敗と食中毒 > #2 微生物を抑えることの大切さ
- Q17.
- 食品添加物は種類が多すぎて、どれが必要でどれがそうでないかわかりません。
- A.
- 食品添加物は科学的に有用性と安全性が確認されたものだけが許可されるということが基本です。また、食品添加物を使うのにもコストがかかりますので、食品メーカーでは不要なものを使うことはないということをご理解ください。
食品添加物がなければ多くの加工食品がつくれなくなり、現在のようなバラエティに富んだ食生活が送れなくなります。砂糖や醤油等を作る上でも食品添加物は欠かせないものだからです。
保存料の場合には、これがなくなると保存性の低下による食品ロスや食中毒の増加等が予想されます。例えば、水産練り製品業界においてソルビン酸の需要が5%低下すると、年間1,773億円の経済損失が生じるという試算があります。
<参考資料>
●「保存料使用減による経済損失と情報提供が消費行動に与える影響」FFIジャーナル Vol.215 No.4(2010)
- Q18.
- 無添加商品が増えていますが、保存料は必要ないのですか?
- A.
- 保存料なしでも食品をつくることはできます。例えば、家庭料理や一般飲食店などでその場で食べてしまう食品、またその日に食べてしまうようなお弁当お惣菜などには保存料は必要ありません。
さらに、食品それぞれの特性(乾燥した食品、キャンディなど)、加工方法(レトルト、塩漬、砂糖漬、アルコール漬など)や保存条件(冷凍、缶詰、脱酸素剤など)によっては、加工食品であっても保存料は必要ありません。
一方で、一般的な練り製品(かまぼこ、竹輪、てんぷら、ハム、ウインナーソーセージなど)、漬物類、珍味類、生菓子、生めん類、調味料類(醤油、味噌、タレ、ソースなど)、調理パン類など多くの加工食品については、食材の安全性確保や廃棄率を下げるために保存料が役に立ちます。
なお、「無添加」と書いてあっても必ずしも保存料が添加されていないとは限りません。「着色料無添加」、「砂糖無添加」などさまざまな無添加があります。保存料の安全性は科学的に根拠付けられていますが、保存料無添加が健康に良いという科学的な根拠は示されていません。
- Q19.
- なぜ、保存料を使用していない食品ばかりにできないのですか?
- A.
- 食品は微生物にとってもおいしい食べ物です。微生物は多様で、熱に強いもの、低温でも増殖できるものなどがいます。例えば、100℃30分で死滅する微生物がいますが、全ての食品にそのような加熱はできません。このように多様な微生物に対応するためには、さまざまな工夫を組み合わせる必要があります。保存料の利用はそのような工夫の一つであり、食べ物をおいしく、安全に食べる上で役立つと考えます。
<参考リンク>
●食品の保存性に影響する要因
- Q20.
- 食塩や砂糖の使用により保存性は高まるのに、保存料を入れる必要があるのでしょうか。
- A.
- 食塩や砂糖を多量に使用して保存性が確保できている場合、保存料を使用する必要はありません。一方、これまで食塩や砂糖を多量に使用して保存性を確保していた食品について、低塩・低糖化を図る際には保存料を使用された方が安全だと考えます。
多量の食塩・砂糖を摂取することは健康への懸念があります。食塩を多く含む食品の摂取と胃がんのリスクとの相関はよく知られているところですし、高血圧等の要因でもあります。砂糖であれば糖尿病のリスクがあります。
ただし、食品の選択は個人の嗜好の問題でもあります。偏りなくいろいろなものを食べられることが最も大切と考えます。
- Q21.
- なぜしらこに含まれるたん白質に保存効果があるのですか?
- A.
- しらこたん白は、ニシンやサケのしらこ(精巣)中でDNAと結合し保護する役割を持っているたん白質です。DNAから分離されたしらこたん白を食品に加えると、今度は細菌等の表面に吸着して生育を阻害し、保存効果を発揮します。
しらこたん白は、ヒトに摂取された際には小腸でアミノ酸にまで分解されて吸収されますので、ヒトの細胞に吸着して健康影響を与えることはありません。
- Q22.
- なぜソルビン酸はハムに使用されるのですか?
- A.
- ソルビン酸はハムに使用することが認められており、広い範囲の微生物に効果があります。さらにハムなどの畜肉製品に対して歯ごたえなどの物性や味に影響が出にくいため適しているとされています。
- このページのトップへ
保存料について
- Q23.
- 保存料とは何ですか?
- A.
- 食品添加物のうち、加工食品の保存性向上の目的で使われるものを保存料といいます。主に微生物による腐敗・変敗を防ぐ役割や、微生物による食中毒を減らす役割があります。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #2 役割や種類
- Q24.
- 保存料にはどのような種類がありますか?
- A.
- 保存の目的で使用される食品添加物として、指定添加物20種類(ソルビン酸やパラオキシ安息香酸ブチルなど)、既存添加物7種類(しらこたん白抽出物やε-ポリリシンなど)が例示されています。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #2 役割や種類
製造方法で分類すると、化学合成で製造される保存料(例えばソルビン酸、安息香酸)、天然物から得られる保存料(例えば、しらこたん白抽出物、ツヤプリシン)及び細菌が作り出す保存料(例えば、ポリリジン、ナタマイシン)があります。
これらの保存料はそれぞれに効果を発揮する条件や微生物菌種が異なることから、使い分けがなされています。
- Q25.
- ソルビン酸は世界で最もよく使われている保存料ということですが、ほとんどの食品に使われているという意味ですか?
- A.
- ソルビン酸は、わが国では使用基準により対象食品が定められています。対象食品については参考リンクをご覧ください。
一方、食品添加物の使用基準は各国により異なり、わが国で使用できない用途に利用されている例もあります。日本国内に輸入できるのは、日本の使用基準に従った食品のみです。
<参考リンク>
●ソルビン酸及びカリウム塩について(詳細)
- Q26.
- 保存料の表示はどうなっているのですか?
日持向上剤など他の食品添加物との違いはあるのですか?
- A.
- 食品添加物は原則として、物質名で表示されます。
しかし、保存料、着色料など消費者の関心が高いとされる用途目的に使用された場合は、物質名の他に用途名を併記するように定められています。
例)保存料(ソルビン酸)
日持向上剤は、保存料と比べると効力が弱いことから区別されており、原則どおり物質名表記のみとなっています。
例)グリシン、酢酸Na
その他に、通常複数の食品添加物の組み合わせにより機能を果たすようなものや、食品中にも常在するようなもので、個々の成分を表示する必要性が少ないと考えられるようなものには、一括名による表示が認められています。一括名には、定義とその一括名を使用できる食品添加物の範囲が定められています。
例)pH調整剤、膨脹剤、豆腐用凝固剤
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #3 食の安全を守る食品添加物
●04 食品添加物の表示
- Q27.
- アミノ酸等と表示されている中に保存料が含まれていると聞いたことがありますが本当ですか?
- A.
- 「アミノ酸等」という表示は、「調味料」について認められているものであり、保存料がこの中に含まれることはありません。
グリシンというアミノ酸が、調味料としても日持向上剤としても使われることがあるためにそのようなうわさが立ったのかもしれません。日持向上剤やグリシンについては参考リンクをご覧ください。
<参考リンク>
●日持向上剤やpH調整剤、酸化防止剤も食品の保存に使われると聞きましたが、保存料とはどう違うのですか?
●「保存料の安全性」のページで例に出ている、「グリシン」、「酢酸Na」、「重曹」、「食塩」とはどんなものですか?
- Q28.
- 保存料はどんな食品に入っていますか?
- A.
- どのような加工食品にも保存料を使用することはできます。ただし、保存料の種類によっては、使用できる食品が限られているものがあります。
保存料の入っている食品には、例えば「保存料(ソルビン酸)」のように、『保存料』の表示がしてあります。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #3 食の安全を守る食品添加物
- Q29.
- 市販で買うものは家でつくるものより腐りにくいと思いますが、保存料が入っているからでしょうか。
- A.
- 食品衛生の基本は、製造現場の衛生管理です。製造現場では業務用の除菌剤を使うなど衛生化を図っています。したがって、家庭でつくったものよりも菌数が少なくなっていることが、市販品が日持ちする第一の理由です。
また、保存料等の食品添加物は、最初から菌数が多いと十分な効果を発揮できません。あくまでも衛生的な製造環境があって、それを補う意味で使われるものです。
- Q30.
- 保存料を使用することによって味に影響はあるのですか?
- A.
- 保存料にも味はありますので、食品の味に影響する場合もあります。
当社のような保存料メーカーでは、日持向上剤やpH調整剤等との併用によって食品添加物全体としての使用量を減らして、味への影響が出ないように工夫しています(したがって、表示が多いからといって添加量が多いとは限りません)。
また、食品メーカーでも、保存性だけを評価するのではなく、味への影響が出ないように厳しく検討を重ねています。
- Q31.
- 保存料は何からつくられるのですか?
- A.
- 保存料の種類によって異なりますので、一概に何からつくられるかとは言えません。ソルビン酸のように化学合成でつくられるもの、しらこたん白抽出物のように天然物から抽出する(取り出す)もの、ポリリシンのように細菌を用いてつくられるものがあります。
- Q32.
- もともとの原料がどんなものなのかわからないので、保存料の入ったものは買いたくありません。
- A.
- 例えば、ソルビン酸は化学的に合成されていますので、「食品でないものを原料にしている」ということが避けられる原因の一つとなっています。
天然由来では一定の品質や量が得られにくい場合が多くあります。化学合成でも天然からの抽出でも、科学的に同じ物質であれば安全性には差がないことをご理解いただきたいと思います。
<参考リンク>
●どうして合成の食品添加物を使うのですか。天然の物で代用できないのですか。
- Q33.
- 保存料は年間どのくらい使われていて、それは一人あたりどのくらいの量になるのですか。
- A.
- ソルビン酸・ソルビン酸カリウムを例にとって説明します。
ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの食品向け出荷量は約850トンと推定されています。一人一日摂取量も、この数字を基に廃棄率等も考慮して推算されており、12.59mg/人/日とされています。この数値は、ADI(一日摂取許容量)の0.9%となります(日本人の平均体重を50kgとした場合)。
なお、 マーケットバスケットという、実際に販売されている食品の分析結果を基にする方式によると、ソルビン酸・ソルビン酸カリウムの1人1日摂取量は5.272mg/人/日(ADIの0.36%)と求められています。
<参考資料>
●「生産統計を基にした食品添加物摂取量推定に関わる研究」JJAFAN、Vol.37、No.3(2017)
●「平成24年度マーケットバスケット方式による摂取量調査」(公財)日本食品化学研究振興財団ホームページ
- Q34.
- 食品企業は保存料を適切に使っているのでしょうか。
- A.
- 保健所が食品メーカーや販売店に立ち入って食品添加物の使用実態の調査を行っています。また実際に食品の検査も行われており、食品衛生法に違反している場合には回収、廃棄等の措置が取られます。
- Q35.
- 保存料にはどのような歴史があるのですか?
- A.
- 食品の保存は、人類の長年の希望と言えます。私たちの祖先は、酢に漬けたり、煙でいぶしたりすると食品が日持することを見出しました。また、岩塩が肉の色を良くし、風味を向上させ、食中毒を起こしにくくすることも利用していました。これは、岩塩に含まれる硝酸塩が、塩漬け中に亜硝酸塩に変化するためであり、現在ハム・ソーセージに亜硝酸塩が使われているのと同じ理由です。このように人類はずっと昔から、食品保存のために化学物質を利用してきたのです。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #1 食品添加物とは
<参考資料>
●「改訂新版よくわかる暮らしのなかの食品添加物」谷村顕雄監修、光生館(2007)
なお、現在の保存料の概念は、食品衛生法が昭和22年12月24日に法律第233号として定められ、この中に保存料も含まれていたことから始まっています。
- Q36.
- 海外でも保存料は使用されているのですか?
- A.
- 国によって承認されている保存料は異なる場合がありますが、海外でも、日本で承認されている多くの保存料が使用されています。
- このページのトップへ
食品添加物全般について
- Q37.
- 食品添加物は誰が決めるのですか?
- A.
- 内閣府の食品安全委員会が安全性を科学的に評価し、消費者庁(※)での審議を経て、最終的には内閣総理大臣の認可により決定されます。
認可までの流れは参考リンクをご覧ください。
※2024年4月1日より食品衛生法による食品衛生基準に関する権限が厚生労働省から消費者庁へ移管されました。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #1 食品添加物とは > 食品添加物はどうやって決められているの?
- Q38.
- 食品添加物の種類・用途にはどのようなものがありますか?
- A.
- 参考リンクにて食品添加物の種類・用途を説明しておりますので、参考にしてください。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #2 役割や種類
- Q39.
- 食品添加物を使用できる食品や量はどのようにして決めているのですか。
- A.
- 食品添加物は、添加物ごとに必要に応じて対象食品や使用量の最大限度等が定められており、これを使用基準と言います。
使用基準は、ある食品添加物をいろいろな食品から摂取しても、一日摂取許容量(ADI)を超えないように設定されています。具体的には、国民健康・栄養調査などから各食品の摂取量を調べ、それに基づいて食品添加物の摂取量を推定し、その量がADIを下回るように設定されています。さらに、実際に摂取量の調査も行われています。
なお、食品常在成分などで使用基準を定める必要性の認められない場合には、使用基準が定められていないこともあります。
<参考リンク>
●「ADI(一日摂取許容量)」とは何ですか?
●05 食品添加物の安全性 > #1 安全性はどのように評価・管理されているか
<参考資料>
●「改訂新版よくわかる暮らしのなかの食品添加物」谷村顕雄監修、光生館(2007)
- Q40.
- 食品添加物製剤とは何ですか?
- A.
- 食品添加物は、安全性の評価を経てリスト化されているものだけを使うことができます。
食品添加物製剤とは、このような安全な食品添加物を組み合わせて製品としたもので、次のようなメリットがあります。
効果を高めることができます。
例えば、ソルビン酸はpHが酸性側で効果を発揮するため、pH調整剤と組み合わせて使用されることが多いです。効果が向上するので、添加量をかえって少なくすることも可能です。
<参考資料>
●「pH」とは何ですか?
味への影響を抑えることができます。
一つの食品添加物のみではその味が食品に出やすくなることがありますが、いくつかを組み合わせることで影響を低減することができます。
計量が容易になります。
食品の製造現場でいくつもの食品添加物を計量するよりも、あらかじめ混合した製剤を使う方がすばやく作業ができます。
また、食品添加物には、食品に対してごく少量しか添加しないものが多いため、計量が困難な場合があります。このような場合でも、あらかじめ他の食品添加物や食品素材と組み合わせておくと計量しやすくなり、誤差も小さくすることができます。
通常は液状のものを粉末製剤化することで、水分の持ち込みを嫌う食品にも使うことができるようになります。例えば、お酢の主成分である酢酸は通常液体ですが、粉末化して食品に使用する技術があります。
保存性を向上させる食品添加物には酸性のものが多いですが、このようなものを直接生の食肉や畜肉などに触れさせるとたん白質を変性させてしまうことがあります。このような場合に、製剤化技術によって品質は維持しつつ、保存効果を発揮させるような設計が生きてきます。
- Q41.
- 日持向上剤やpH調整剤、酸化防止剤も食品の保存に使われると聞きましたが、保存料とはどう違うのですか?
- A.
- 「日持向上剤」とは、保存料ほど微生物に対する効果はありませんが、保存性の低い食品に用いられて短期間での腐敗や変敗を抑える食品添加物を指します。食品業界で用いられる言葉で「日持向上剤」という表示はされません。
保存料が微生物による食品の腐敗や食中毒リスクを抑える目的なのに対し、「酸化防止剤」は、酸化による食品の変質を防ぎます。食品の酸化には、ジャムやお茶の変色、干魚の色や風味の劣化などがあります。
「pH調整剤」は、食品のpHを調整する働きをもつものです。pHを調整することで保存料や日持向上剤、酸化防止剤の効果を向上させることができます。また、pHを酸性にすることで微生物が増えにくくなります。他に、イチゴジャムの色やゼリーの食感などの変化を抑える働きもあります。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #2 役割や種類
●「pH」とは何ですか?
- Q42.
- 日持向上剤はなぜ日持向上剤と表示されないのですか?
どうすれば日持向上剤だと分かりますか?
- A.
- 日持向上剤は、保存料と比べると効力が弱いことから区別されており、原則どおり物質名表記のみとなっています。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #2 役割や種類
なお、日持向上剤として使用される食品添加物には、pH調整剤、酸味料、調味料等としても使用されるものがあります。例えば、グリシンは日持向上剤として使用されるアミノ酸ですが、イカやエビの呈味成分としても知られており、調味料として使われる場合もあります。このように複数の効果を発揮する食品添加物を使用する場合は、それを使用する主目的から表示方法を決めることになっています。
<参考リンク>
●04 食品添加物の表示
- Q43.
- 食品添加物とそうでないものとが分かりやすいように表示を工夫してほしい。
- A.
- 食品メーカーでは法令に従って食品原料→食品添加物の順に表示していますので、ある程度区別しやすくなっていると思います。
2015年4月に施行された食品表示法では、食品原料と食品添加物との間にスラッシュ(/)を入れるなどをして、明確に区分することが定められました。5年間の経過措置期間がありますので、徐々により分かりやすいように変わっていきます。
一方、海外の多くの国では食品原料と食品添加物との区別なく量の多いものから順に表示されています。この場合、食品原料と食品添加物との量の関係が分かるというメリットがあります。
- Q44.
- 私たちは食品添加物を1日にどのくらい摂取しているのでしょうか?
- A.
- どのような物質でもそうですが、食品添加物もひとつひとつ一日摂取許容量(ADI)が異なります。したがって、食品添加物の摂取総量から安全性を議論することは難しいことをあらかじめご理解下さい。
厚生省(当時)の90年代の調査では、食品添加物をA群(未加工の食品には含まれないもの)、B群(未加工の食品にも含まれるもの)に分けて日本人の一日あたり摂取量を調べています。
その結果の概略は以下のとおりです。
◆ A群添加物:0.08~0.12g/日の摂取量でした。個別の食品添加物について一日摂取許容量(ADI)と比較すると、いずれもADIの3%以下でした。
◆ B群添加物:この中には未加工の食品(加工食品の原料食材や生鮮食品)にもともと存在する物質が含まれています。加工食品由来が9.42g/日、生鮮食品由来が 6.68g/日の摂取量でした。なお、このうち食品添加物由来は2.67g/日と推定されています。
ちなみに、A群添加物にはプロピレングリコール、ソルビン酸、アスパルテームなど、B群添加物にはキシリトール、ソルビトール、グルタミン酸などが含まれています。
<参考資料>
●伊藤誉志男、Foods & Food Ingredients Journal of Japan, 212, 10, p815 (2007)
- Q45.
- 日本食品添加物協会や自治体、貴社など資料によって指定添加物、既存添加物の数が違うのはなぜですか?
- A.
- 指定添加物の数は近年増えています。これは主として、国際的に安全性が確認され、かつ汎用されている食品添加物の審査・指定が進められているためです。
諸外国では広く使用されている食品添加物で、日本では認可されていないものがあると、その食品添加物を使用した食品は輸入することができません。このような状況は好ましくないということで、安全性の評価や審査、指定が進められています。
一方、既存添加物は1995年には489品目ありましたが、2020年には357品目となりました。これは、流通実態のないものがリストから外されたことによります。
今後も増減のある見込みです。最新の食品添加物の数は、(一社)日本食品添加物協会のホームページにて迅速に更新されていますのでご参照ください。
<参考リンク>
●(一社)日本食品添加物協会
- Q46.
- 海外で使用されていて、日本では許可されていない食品添加物はあるのですか?
- A.
- 食品添加物の規制は国ごとに実施されていますので、国によって許可されている食品添加物の種類や使用基準が異なっています。
日本で許可されていないけれども、他の多くの国で使用されている食品添加物もあります。
この場合には、加工食品の輸入の際に無認可添加物が検出されて問題となることがあるため、国際的に安全性が確認され、かつ、広く使用されている食品添加物については、国際的な整合性を図るべく認可が進められています。
- Q47.
- 日本で使用されていて、海外で許可されていない食品添加物はあるのですか?
- A.
- いわゆる天然添加物(現在は既存添加物に分類)には日本でしか許可されていないものが多くあります。これは、日本では天然由来の方がイメージが良いとされること、以前は食品添加物の指定は化学合成品のみが対象とされていたことなどを理由として、独特のものが開発されたためです。
なお、1995年には天然系の食品添加物も含めて指定する制度に移行し、それまで使用されてきたいわゆる天然添加物489品目は例外的に既存添加物として使用が認められることになりました。これまでに流通実態が確認できないものの消除が進められ、現在では既存添加物名簿収載数は357品目となっています。これらの中には十分な安全性評価が済んでいないものもあり、現在評価が進められています。なお、アカネ色素という天然色素については発がん性が疑われたため、速やかに使用禁止とされました。
- このページのトップへ
用語説明
- Q48.
- 「pH」とは何ですか?
- A.
- pHは0~14の数値で物質の酸性~アルカリ性を表すものです。pH = 7を中性といい、数値が小さいほど酸性が強く、大きいほどアルカリ性が強いことを表します。
例えば、酸性の食品としてレモン(果汁のpH 2.2~2.4)、白ワイン(pH 3.0~3.4)、中性付近の食品として魚肉(pH 6.2~6.6)、ゆでめん(pH 6.5)、アルカリ性の食品としてこんにゃく(pH 8.0)などがあります。
<参考資料>
●「微生物制御の基礎知識」藤井建夫、中央法規出版(1997)
大部分の細菌にとって、増殖に適したpHは6.0~7.5の中性付近です。カビや酵母はpH 4.0~6.0の酸性側でよく増殖します。これらの微生物(細菌、カビ、酵母等)が食品中で増殖するのを防ぐために、食品のpHをコントロールすることは有効とされています。
<参考リンク>
●食品の保存性に影響する要因
- Q49.
- 「水分活性」とは何ですか?
- A.
- 水分活性とは、食品中の自由水(微生物が利用できる水分)の割合を表す数値です。水分活性が低いほど自由水が少なく(=微生物が増殖しにくく)、高いほど自由水が多い(=微生物が増殖しやすい)ことを表します。
食品においては、水分活性を低くすることにより、微生物の増殖を抑制し、保存性を高める因子の1つとして利用されています。
<参考リンク>
●食品の保存性に影響する要因
●塩分や糖分が食品保存に果たす役割
- Q50.
- 「トータルサニテーション」とは何ですか?
- A.
- ウエノフードテクノでは食品の微生物コントロールは、衛生的な製造環境と、“食品を内から守る”食品添加物、“食品を外から守る”ガスコントロール技術等の組み合わせで実現するものと考えています。これをウエノでは、トータルサニテーション(直訳すると「総合的衛生化」)と呼んでいます。
<参考リンク>
●ウエノのトータルサニテーション(株式会社ウエノフードテクノのコーポレートページ)
- Q51.
- 「キャリーオーバー」とは何ですか?
- A.
- キャリーオーバーの定義については参考リンクをご覧下さい。
<参考リンク>
●04 食品添加物の表示
例えば、保存料である安息香酸が添加された醤油でせんべいの味付けをした場合、微量の安息香酸がせんべいに含まれることになります。しかし、このように微量の安息香酸は保存料として効果を持つ量よりはるかに少量で、せんべいの保存性に影響しないのでキャリーオーバーとみなされて表示が免除されます。
<参考資料>
●「新食品添加物表示の実務」食品添加物表示問題連絡会、日本食品添加物協会共編
- Q52.
- 「しらこたん白」って何ですか?
- A.
- 主にサケやニシンのしらこ(精巣)から得られるたん白質のことです。これらのたん白質は細菌の増殖を防ぐ効果を持っており、保存料として用いられます。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #3 食の安全を守る食品添加物
●05 食品添加物の安全性 > #3 ソルビン酸としらこたん白の安全性
- Q53.
- 「ソルビン酸」って何ですか?
- A.
- ソルビン酸は、脂肪を構成する成分である脂肪酸の一種です。脂肪酸には抗菌性を有するものが多いですが、ソルビン酸は風味への影響が少ないことから、食品向けの保存料として世界で最も多く用いられています。わが国では1955年に食品添加物として指定されました。
ソルビン酸の使用について、わが国では使用基準(対象食品、使用量の最大限度)が定められています。対象食品によって異なりますが0.3%以下の使用量です。一方、米国では、「砂糖」や「寒天」と同等の使用制限なしのGRAS (Generally Recognized As Safe)物質として扱われています。
ソルビン酸は化学合成により製造されています。通常、未加工の食品には含まれていませんが、クラウドベリーの果実中に含まれているという報告もあります。体内では、通常の脂肪酸と同様に二酸化炭素と水に分解されると考えられています。
<参考リンク>
●03 食品添加物の役割と利用 > #3 食の安全を守る食品添加物
●05 食品添加物の安全性 > #3 ソルビン酸としらこたん白の安全性
- Q54.
- 「急性毒性」とは何ですか?
- A.
- 安全性の試験には発がん性試験、慢性毒性試験、催奇形性試験などいろいろありますが、急性毒性試験はその一つです。急性毒性試験では、実験動物にある物質を一回または短期間に複数回与えて半数致死量を求めます。最近は動物愛護上の理由から概略の致死量を求める試験に変更されています。 なお、無毒性量や一日摂取許容量(ADI)はさまざまな安全性試験の結果から求められており、急性毒性試験の結果のみから決められることはありません。
<参考資料>
●「食品の安全性評価のポイント」監修:林裕造、国際生命科学研究機構(2007)
<参考リンク>
●食品の安全性に関する用語集(食品安全委員会)
- Q55.
- 「半数致死量」、「LD50」とは何ですか?
- A.
- 半数致死量は、Lethal Dose 50、50% Lethal Doseとも言われ、それを短縮してLD50と表記することがあります。急性毒性の指標で、実験動物にある物質を与えた場合に、ある日数のうちに半数(50%)を死亡させたと推定される量を言います。通常はmg/kg体重で示し、数値が小さいほど毒性が強いことを表します。
<参考リンク>
●食品の安全性に関する用語集(食品安全委員会)
- Q56.
- 「安全係数」とは何ですか?
- A.
- 動物実験結果からヒトの一日摂取許容量(ADI)を求める際に、更に安全性を考慮するために用いる係数のことです。『動物における無毒性量÷安全係数=ADI(ヒトの一日摂取許容量)』となります。
安全係数としては通常、100が用いられます。動物とヒトとの種差として「10倍」、さらにヒトとヒトとの間の個体差として「10倍」の安全率で通常は十分であることが知られており、それらをかけ合わせた「100倍」であるとされています。データの質によっては、より大きい係数(例えば500 、1000 、1500 など)が用いられることもあります。
<参考リンク>
●食品の安全性に関する用語集(食品安全委員会)
- Q57.
- 「ADI(一日摂取許容量)」とは何ですか?
- A.
- Acceptable Daily Intakeの頭文字をとって、エーディーアイとよばれています。ヒトが一生毎日食べ続けても健康に悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量のことです。通常、体重1kgあたりの物質量で示されます(例:mg/kg体重)。
例えば、ある物質のADIが25mg/kg体重である場合、体重50kgのヒトは一日あたり1,250mg(=25×50)を毎日摂取しても、健康への悪影響がないと考えられます。
<参考リンク>
●食品の安全性に関する用語集(食品安全委員会)
- Q58.
- 「食品添加物の安全性」のページで例に出ている、「グリシン」、「酢酸Na」、「重曹」、「食塩」とはどんなものですか?
- A.
- 「グリシン」は、たん白質を構成するアミノ酸の一種であり、長年の食経験があります。日持向上剤や調味料として使用される食品添加物です。
「酢酸Na」は、pH調整、風味の向上、日持ち向上などの効果があり、pH調整剤、酸味料、日持向上剤などとして使用されます。
「重曹」は炭酸水素ナトリウムのことで、膨脹剤としてお菓子作りなどで使用されるほか、かんすい、pH調整剤として使用されることもあります。
「食塩」は家庭にある食塩のことです。食品添加物ではありません。
<参考資料>
●「改訂新版よくわかる暮らしのなかの食品添加物」谷村顕雄監修、光生館(2007)
- このページのトップへ
その他
- Q59.
- 腐敗と食中毒はどう違うのですか?
腐敗したものを食べるから食中毒になるのではないのですか?
- A.
- 腐敗は、食品に微生物が増殖した結果、食品本来の味、香りなどが損なわれ食べられなくなる現象を言います。微生物の種類が特に限定されるわけではなく、一般に腐敗した食品を食べても下痢など特定の症状は見られないことが多いです。
食中毒には、微生物由来のもの、自然毒(フグ、キノコなど)由来のものなどがあります。そのうち微生物由来の食中毒は、特定の病原微生物が原因となるもので、食品本来の味、香りなどが損なわれていなくても食中毒は起こります。
<参考資料>
●「食品微生物II 制御編 食品の保全と微生物」藤井建夫編、幸書房(2001)
<参考リンク>
●02 食べ物の腐敗と食中毒 > #1 腐敗や食中毒を起こす微生物
- Q60.
- 賞味期限はどうやって決められているのですか?
- A.
- 賞味期限とは、缶詰やレトルト食品など、製造・加工からおおむね6日以上日持ちする食品に表示され、安全性や味など品質を保証する期限を示しています。
賞味期限の決定は、各事業者が責任をもって行なうもので、通常はまず科学的・合理的な根拠(理化学試験、微生物試験、官能検査などの結果)に基づいて品質が保持される期限を求め、その期限に対して1未満の安全係数をかけて決定されています。
<参考リンク>
●消費期限・賞味期限
- Q61.
- どのくらいの食品が廃棄されているのですか?
- A.
- 農林水産省は、食品ロス削減の取組の進展に活かすため、食品ロス量の推計を行い公表しています。2021年度の推計値によると、まだ食べられる部分の廃棄量(食品ロス)は約523万トンとされています。家庭からの廃棄はそのうち約244万トンであり、賞味期限切れや食べ残し等が要因とされています。
<参考リンク>
●02 食べ物の腐敗と食中毒 > #2 微生物を抑えることの大切さ
- Q62.
- 食品衛生法とはどんな法律ですか?
- A.
- 食品衛生法は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するために昭和22年に法律第233号で制定された法律です。食品と食品添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定めています。
<参考リンク>
●「厚生労働省 食品安全情報」
- Q63.
- 食品添加物の安全性はどこの機関が担当しているのでしょうか。
- A.
- 内閣府の食品安全委員会が安全性を評価し、消費者庁(※)がそれに基づいて許可するかどうか、使用量をどのように規制するか等の管理を行っています。このように役割分担されチェックが入る構造になっています。
※2024年4月1日より食品衛生法による食品衛生基準に関する権限が厚生労働省から消費者庁へ移管されました。
- Q64.
- 食品安全委員会とは何ですか?どんな人がなるのですか?
- A.
- 食品安全委員会は、食品を摂取することによる健康への悪影響について科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に評価を行なう目的で、平成15年7月1日に内閣府に設置されました。
食品安全基本法に従って、食品の安全性確保のための規制や指導を行ない、リスク管理機関(消費者庁や厚生労働省など)から独立した機関となっていることが特徴です。
食品安全委員会は、食の安全に関し深い見識を有する7名の委員から構成され、その下に16の専門調査会が設置されています。またこれらの運営のために事務局が設置されています。
<参考リンク>
●「食品安全委員会」
- このページのトップへ